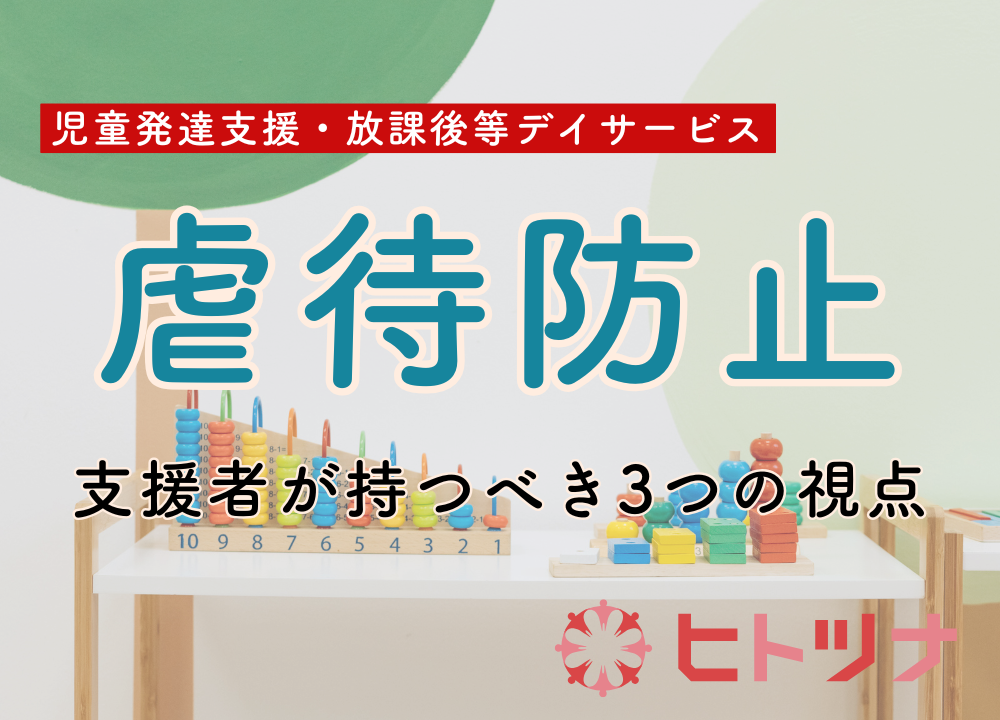はじめに
放課後等デイサービスの現場において「虐待防止」は最も重要なテーマです。虐待というと極端な事例を思い浮かべがちですが、実際には「無意識の対応」が子どもを傷つけてしまうこともあります。
だからこそ、私たち支援者は日々の関わりの中で「何を大切にするか」という軸を持っていなければなりません。ここでは、虐待防止のために欠かせない3つの視点――倫理観・美意識・感性について解説します。
倫理観 ― 子どもの人権を守る基盤
倫理とは、社会の中で人が正しく生きるための「道しるべ」であり、人と人との関わりの中で何を守り、どう振る舞うかを示す価値基準です。支援の現場に立つ私たちにとっての倫理は、目の前の子どもの安心と尊厳を第一に考える姿勢を意味します。
支援者が「何が正しいのか」「どうあるべきか」を判断し、虐待防止を考える上で、倫理観は最も根本的な土台になります。
特に保育士には「保育士倫理綱領」があり、子どもの最善の利益を守ること、子どもの人権を尊重すること、そして保護者や地域との協力を大切にすることが明記されています。
放課後等デイサービスで働く保育士や支援者は、この職業倫理を常に意識して行動することが求められます。
忙しさで、感情に流されてしまう場面への葛藤は現場に多くあります。
限られた人員での支援に余裕を失ったりする時もあるでしょう。
そんな時こそ「これは本当に子どもの利益につながっているだろうか」「自分の感情で子どもを扱ってはいないだろうか」と立ち止まることが重要です。
倫理観は、単にルールやマニュアルを守ることではありません。
子どもを一人の人として尊重し、安心と安全を第一に考える姿勢そのものです。
保育士の専門性は、子どもの育ちを支えつつ、社会的にサポートが必要な立場にある子どもの権利を守る責任を担っています。
その責任を果たす心の拠り所こそが、支援者にとっての「倫理観」なのです。
美意識 ― 規範を大切にし、より良い関わりを選ぶ姿勢
美意識という言葉は見た目の美しさを連想させますが、ここでいう美意識はもっと深い意味を持ちます。それは 「規範を守ろうとする姿勢」や「倫理観を大切にする心構え」そのもの です。
「当たり前の事(倫理)を守れているか」、「子どもの尊厳を損なっていないか」と問い直すこと。
美意識とは、単に不適切な行為を避けるのではなく、より良いあり方を選ぼうとする態度です。
支援の現場は効率や業務の流れに流されやすい場所ですが、そこであえて「より良くあろう」とする姿勢が、美意識です。
これは倫理観を現場に実践的に落とし込む力でもあり、現場全体の雰囲気を変える大切な要素になります。
感性 ― 自分たちの行動のズレに気づく力
感性というと「子どもの小さなサインに気づくこと」を思い浮かべがちですが、施設における虐待防止の観点では、自分たちの関わりが倫理観や美意識からズレ始めていないかを感じ取る力が大切だという考えがあります。
例えば「忙しいから少しくらい手を抜いてもいいか」「言葉がきつくなってしまったけど仕方ないか」「子どもも笑っているからいいか」といった、日々の延長にある小さな違和感、出来事。
放置すればそれが積み重なり、虐待につながることがあります。
また「はじめは遊びの延長だったが徐々に行き過ぎた戦いごっこ」や「子どもへのからかい」等、愛情があるからといって踏み越えてはいけない線を越えてしまうこともリスクの一つです。
感性とは、そうした“日常の小さなズレ”にいち早く気づき、「このままで大丈夫だろうか」と立ち止まれる力です。
つまり感性は、倫理観(子どもの人権を守る基盤)と美意識(規範を大切にしより良い関わりを選ぶ姿勢)を現場で維持し続けるためのセンサーです。支援者一人ひとりが感性を研ぎ澄ますことで、無意識に生まれる虐待の芽を早い段階で摘み取ることができます。
まとめ
虐待防止は「規則を守ること」だけでは実現できません。
- 倫理観=子どもの人権を守る基盤
- 美意識=規範を大切にし、より良い関わりを選ぶ姿勢
- 感性=自分たちの行動がズレていないかを察知する力
この3つを意識し、日々の支援に生かすことが、子どもの安心と未来を守る大きな力になります。支援者一人ひとりの在り方こそが、虐待防止の最前線なのです。
お問い合わせ・研修のご相談
ヒトツナでは、放課後等デイサービスや児童発達支援の現場に合わせた 虐待防止研修・職員研修 を実施しています。
- 現場に即した事例共有
- 発達特性を踏まえた関わり方
- 施設全体で取り組む虐待防止の仕組みづくり
研修や相談をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
👉 [無料個別相談はこちらから]