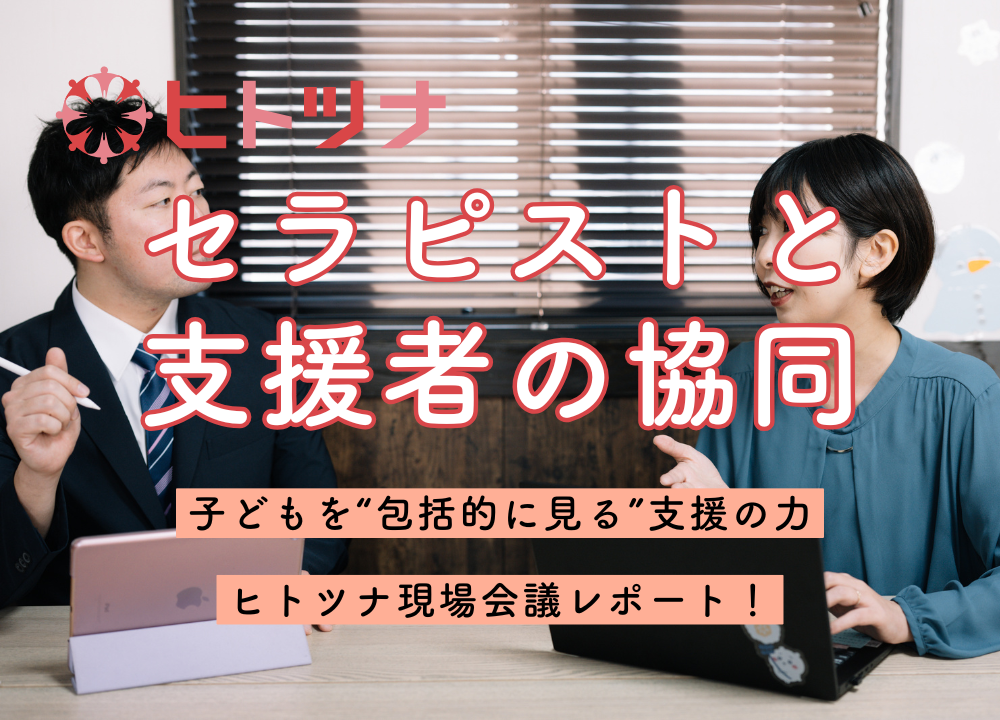児童発達支援・放課後等デイサービスヒトツナフランチャイズ本部です!
本日のコラムでは、9月16日に開催された、ヒトツナ各教室による「専門職Meet-up!」(以下、ミートアップといいます)の様子について、共有させて頂きます。
この取り組みは、各教室に所属している理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、児童福祉経験5年以上の保育士及び児童指導員が参加し、事業所における「専門職」としての経験共有を行うものです。
ヒトツナグループでは、今年度より管理者、児童発達支援管理責任者、支援者、専門職のそれぞれのグループでミートアップを開催し、各教室や個々人に蓄積されたナレッジの共有を図る取り組みを行っております。
今回の参加者たちは、専門的支援実施計画に関連する部分を担う立場として、子どもたちとの関わりや評価方法について議論し、プレイベースの評価や子ども同士お互いの意思を尊重する対応などの専門知識を共有しました。
会議では問題行動の対応についても議論され、状況全体を考慮した観察と包括的なアプローチの重要性が強調される会となりました。
専門職による子ども支援議論
登場専門職:理学療法士、作業療法士、心理指導担当職員、保育士、児童指導員、児童発達支援管理責任者など。
テーマ:子どもへの関わり方や評価方法。
主な論点
- 理学療法士は「評価基準や観察の仕方」に迷いを感じており、プレイベース(遊びを通じた)評価や観察の重要性が指摘された。
- 保育士は「子ども同士の気持ちのぶつかり合い」への対応方法を質問。これに対しては、心理指導担当職員より、他者の視点を意図的に取り入れることが重要と共有された。
- 全体を通じて、チームでの連携、個別支援計画の実施を通じて、多職種で子どもを包括的に理解することの意義が強調された。
問題行動とされる行動への介入について
ファシリテーター:ヒトツナグループ本部 遠藤千尋
主な事例と議論
- 作業療法士からは「感覚的要因が問題行動につながる可能性」が報告され、突発的な行動を示す子への対応として、視覚的・聴覚的、様々な感覚刺激に対する反応についての評価・観察が助言された。
- 理学療法士からは「減速と加速」等、動きについての評価を行うよう助言され、人や物の回避スキルや、動きが加速している状況での視覚的・聴覚的な周囲への反応の観察が提案された。
遠藤千尋のまとめ
- 問題行動を検証する場合は、応用行動分析に基づき行動の前と後の対応を観察していくことは基本となると解説した。その上で、問題行動そのものが「強化子」になっている可能性について言及した。
- 問題行動そのものが「強化子」となっているような場合は、その行動への興味関心やこだわりが強くなっている可能性があり、一時的で治まる可能性もあると考えられる。問題行動そのものが強化子になっていると想定されるケースでは、事前の環境設定として代替的な活動の導入により問題行動の発生頻度の減少を図るとともに、その状態を更に強化していくことを提案した。
- 一方で、問題行動そのものが「意思」を通すための手段となっているケースでは、その根本への支援が求められる。但し子ども本来の発達過程において意思表出や形成についてはだれしも発達の途上であり、「自然と伸び行く部分」についても否定しないかかわりが必要だと求めた。
- 問題行動の対応では「その場面だけでなく状況全体を捉える観察」が重要。
- さらに、身体的・感覚的・知的な状態を含めた包括的アプローチを行うことの必要性を強調した。
多職種が連携しながら、子どもの行動を単発で評価するのではなく、環境・感覚・発達を含めた包括的視点で理解しようとする姿勢 にある、というのが今回のミートアップの結論となりました。
一人では見えない子どもの姿も、チームでなら捉えられます。
子どもの行動を“問題”ではなく“成長のサイン”として受け止める。
そんな支援を地域で広げていきたい方へ。
👉 ヒトツナフランチャイズの詳細資料を請求する